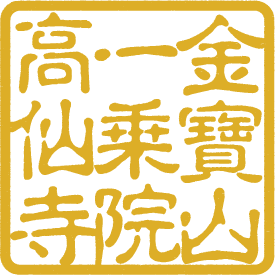弁才天
(中央)
大弁才功徳天・妙音天とも呼ばれ、弁財天とも言われる。
もとは、インドの河の神、農業神であったが、
福徳・商売・財運・言語・学問・音楽・芸能などの神として崇拝される。
御使いは白蛇。
以前から、上山市二日町近辺の商店主等から商売・財運の面から崇拝され、
また上山市新湯等の芸者衆からは芸事の技芸の向上の面から崇拝され、祭典も行なわれた。
この弁才天は、高さ5寸で護摩の灰で固めて作ったものとされ、
その背中に「空海」の文字があるとされる。
普段は秘仏であるが、巳年の時の祭礼の時に開帳することとしている。
弁才天の納まっている厨子は、近年修復したもので、
裏書きなどから長谷川家の先祖から寄進されたものであると推定することができた。
また、飾り金具の作成の仕方が、山形仏壇の飾り金具の作成方法と違うことから、
京都の仏師・職人が作成したものと推定される。

大黒天
もとはインドの戦闘神で、寺院守護神である。
日本では、大国主命と同一視され、財福神として広く信仰を集める。
御使いはネズミ。
この大黒天は財福神ということから弁才天とともに、崇拝を集めている。
明治から大正時代にかけて、上山市内で大力という商号で商売をしていた、
後藤治三郎氏等が寄進をしている。
後藤治三郎氏は実業家で、仙石の町内すべての道路の敷石を寄付しているような財産家であった。

歓喜天
大聖歓喜天の略で、聖天、天尊ともいわれる。
福徳・財運・夫婦和合・子孫繁栄等のあらゆる願望を成就させる神として、崇拝される。
御しるしは巾着袋、二股大根である。絶対の秘仏としている。
近年、聖天像の納まる厨子、円檀等の修復をしたところ、
裏書などから相馬家の先祖から寄進されたものと推定された。

毘沙門天
多聞天とも呼ばれる。四天王、十二天、十六善神の一神である。
現世利益の神として信仰をあつめ、七福神の一神である。
この毘沙門天は、財福神ということから、弁才天とともに崇拝を集めている。

大燈籠
門前に大燈籠がある。
明治から大正時代にかけて上山市内で大力という商号で商売をしていた、
後藤治三郎氏が寄進をしている。
燈籠のところに「大力」という商号が彫られている。
燈籠に彫られているネズミや丑、寅の彫刻から、十二支が彫られていたと思われ、
本来、一対のものであったと推定される。
近年、修復した時に山形市銅町で鋳造されたものと推定された。
また、同じような燈籠が四国の金毘羅神社、宮城の金華山神社に
奉納されているということである。